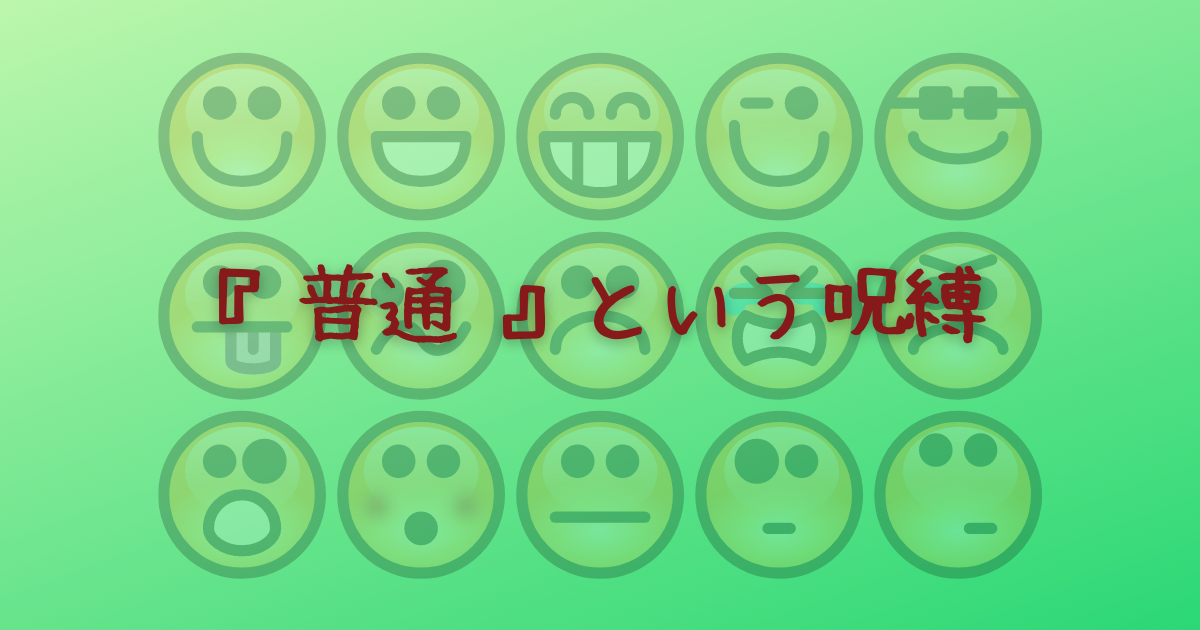
『普通に生きる』
『普通の家庭』
『普通の考え』…etc.
世の中に溢れる”普通”という言葉。
私、ねっくはその言葉を言われる度に、少しだけ苦しんでいました。
『何故、周りが”普通”に出来ていることが出来ないの?』
『こっち方が”普通”じゃない?』
『”普通”こうだよ』
その”普通”という言葉が私にとっても”普通”だったので、苦しみつつも受け入れていました。
しかし、自分がグレーゾーンだと認知してから”普通”という言葉をそのまま
考えなしに受け取るのは良くないのではないかと感じるようになったのです。
どういうことか?
簡単に言うと、普通という言葉の認識が十人十色なためです。
例えば、労働時の”普通”について考えます。
仕事をしていて、ミスをした際に上司から叱責を受けたとします。
ミス自体は自分のせいなので、怒られるのは仕方ないと感じているけれども
怒り方が厳しすぎて心が辛くなったとしたら、いかがでしょうか。
以下の2パターンだと、どちらが近いでしょうか。
≪Aパターン≫
仕事なのだから上司が部下に対して指導するのは普通である。
むしろ、怒られない方が見放されてると考えるべき。
≪Bパターン≫
仕事とはいえ、部下が傷付いたり、委縮するような伝え方は良くない。
今の時代は、感情的にならず聴き手に伝わるように言うのが普通である。
どちらも決定的に間違っているとは言えないと思いませんか。
この二つは見る角度と、立場が違うだけなのです。
ただ、一番のズレは仕事(働く)ということへの認識の違いなのでしょう。
Aパターンは、
『仕事はお金を稼ぐために来ている。働くということは多少の辛さも耐えるものだ』
という認識が根っこにあるのでしょう。
一方、Bパターンは
『働いていて、立場の差があろうと、上司が威圧的になるべきではない。伝える努力をすべき』
という認識でしょう。
この両極端の考え方すら包括的に言えてしまうのが”普通”という言葉の
便利で不便な特性だと思っています。
玉虫色の言葉を皆が使うから、認識違いが起こってすれ違う要因になるのです。
私はこれからの時代で必要なのは、対話する努力なのだと思っています。
上司と部下
先輩と後輩
親と子
様々な関係性があれど、話しているのは人間同士です。各々の”普通”があるのです。
立場は置いておいて、フラットに対話できる場が無いと、ずっと認識のズレが埋まらないのです。
私の意見も、Aパターンの人から見たら、”甘い”でしょうし、”普通ではない”のでしょう。
でもそれも、対話して関係性を作れるならオープンに話が出来るはずです。
その対話こそが、様々な価値観を受け入れられる土壌だと思っています。
私の記事が、誰かにとって何かの役に立ちますように。